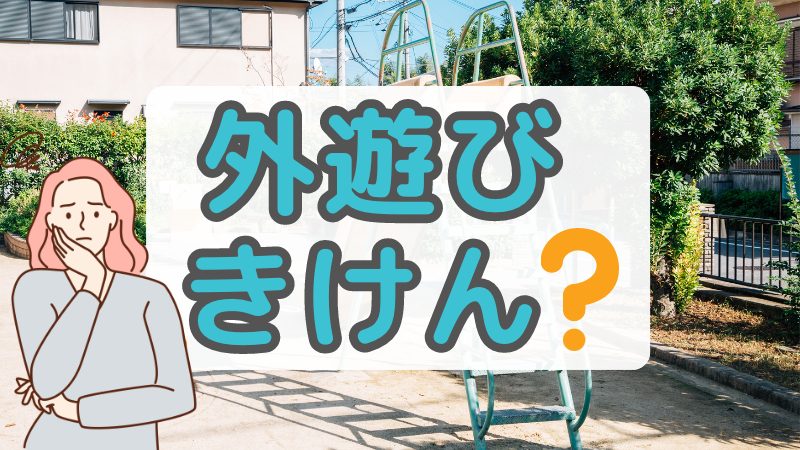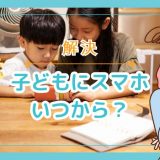この記事では、
- 幼児の外遊びにおけるメリットとデメリット(ケガなどのリスク)のバランスの重要性
- 親は、どのように子どもの成長・発達をサポートできるか
について探ります。
記事で紹介されている商品を購入すると、売上の一部がロジカル育児に還元されることがあります🌱
安全すぎる遊具では、外遊びのメリットを享受できない

親として、そしてライターとして、近所の遊び場で他の親子のやりとりを観察することがあります。
子どもが新しいことに挑戦しようとすると、「危ないからやめなさい」と言う人。「お友だちが待ってるよ、早くしなさい」と、せかす人。また、子どもが滑り台を逆走すると、「滑り台は上から滑るものでしょ、やめなさい!」と注意する人まで。(「誰も上にいないんだから、別にいいじゃん!」と横入りしそうになるのを、グッと堪える
私は、このような態度には疑問を感じます。そして同時に、自分も同じように注意しないと、「非常識な親だ」と思われるかもしれないとも悩みます。
しかし私はここで、ケガやトラブルを経験しても、子どもには外遊びを楽しむ権利があると主張したいのです。
日本では、安全性を追求するあまり、「危険な」遊具を撤去することがよくあります。
ケガが報告されるたびに遊具が消えていき、砂地だけになった公園を探すのは難しいことではありません。
このようなアプローチでは、子どもが適切なリスクを取る機会や、経験から学び、レジリエンスや対処法を身につける機会が制限されます。
これは社会全体にとっても、喪失です。

一方、ヨーロッパでは遊びの環境を整備するため、リスク・ベネフィット・アセスメントという基準が用いられます。
これは、遊具で遊ぶことのデメリット(ケガなどのリスク)と、得られるメリット(発達や能力アップなどのベネフィット)を比較し、メリットが大きいと判断される場合に遊具の利用が許可されるという考え方です。
ヨーロッパでは、年間数万件の事故事例を正確に収集し、重症度に関わらず慎重に検討しています。
例えば、遊具から落ちて腕を骨折する事故が起きた場合、それは許容できるリスクと判断されます。骨はそのうちくっついて元通りになるからです。
一方、日本では腕の骨折から死亡事故まで、すべてを一括りにして安全対策を推し進めます。
外遊びのリスクを許容する親になる
このような、メリットとデメリットのバランスをとるアプローチは、遊具の安全判断だけでなく、あらゆる子育てシーンに応用できます。
例えば、私は娘が初めて高い滑り台に挑戦する時、鳩尾がキュッとしたのをおぼえています。しかし親として、私は娘が適切なリスクを取ることを許さなければなりませんでした。そしてその選択は正解でした。
いま娘はいろんな身体の動かし方を学んで、外遊びのメリットを最大限に享受しています。

私たち家族は、挑戦的な遊びを歓迎する場所に出かけることが好きです。
そのひとつが全国展開されている冒険遊び場(プレーパーク)です。
火おこし、泥遊び、スケボー、木工、秘密基地づくりなど、プレーリーダーと呼ばれるボランティアの監督のもと、あらゆる危険な遊びが許可されています。
これは文字通り子どもたちが冒険し、リスクを取りながら、経験から学ぶための空間です。(わざわざ遠征する価値のある場所です!探してみてね

もちろん、ケガをしない、ケガをさせない、お友だちとトラブルにならないように周囲に気を配ることは、人として正しい行いです。しかし、そこに過度にこだわると、子どもは何もできなくなってしまいます。
多少のケガやトラブルは、人生の学習プロセスの一部でしかないと、大人から意識を変えることが大切です。
このテーマについて、個人的な経験や考えをぜひシェアしてください!子どもたちが自由に遊び、リスクを取りながら成長することを支援する意識の共有が進みますように!
日本では遊具の危険度を、どんな「基準」で審査しているのか疑問に思いませんか?
全国で大型遊具の設置を行っている株式会社アネビーのサイトに、日本の安全基準が作られた経緯がわかりやすく書いてあります。(私はたまたま企業向け展示会で株式会社アネビーのセミナーを聴講し、知りました。そして、厳格に守られている安全基準が、子どものことを一切考えずテキトーに作られたことを知り、腑が煮えくり変える思いをしました。)
ご興味ある方は、ぜひぜひ以下のコラム2つをお読みください。