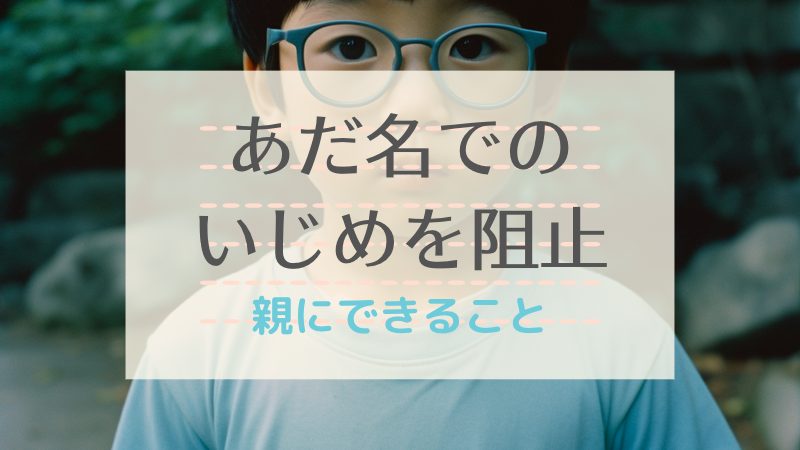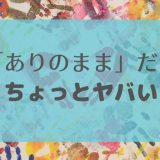記事で紹介されている商品を購入すると、売上の一部がロジカル育児に還元されることがあります🌱
「メガネマン」と呼ばれた息子

息子は、3歳の保育園児。ある日お迎えに行ったら、
「最近Sくんに、メガネマンっていわれる」
といいました。息子は、小児弱視と診断され、小児用メガネをかけて登園しています👓
Sくんは、たしかに言葉が乱暴なところがありますが、人懐っこくてかわいらしい男の子です。息子には申し訳ないのですが、私の頭によぎったのは「波風立てたくないな・・・」という思いでした💦
おそるおそる「メガネマンといわれて、あなたはどう思ったの?」と聞いてみました。
すると、息子はにやりと笑って「いいと思った」というのです😳
どうやら、自分にだけ特別なあだ名がついたことを「かっこいい」と思ったようです。なんとお気楽なことでしょうか😅
しかし私は、親として「メガネマン問題」を看過しないことに決めました。そして、すぐに連絡帳で担任の先生とコンタクトをとりました。翌日にはクラスで話し合いの時間が設けられ、「メガネマン問題」は鎮火しました。
あだ名でいじめられそうになったら、親がやるべきこと3つ
わが子が変なあだ名で呼ばれていることに気づいたら、動揺します。「なんとかしなきゃ」と思って、こんな行動にでるかもしれません。
- すぐに担任や相手の親に連絡をとって、解決のために行動する
- 「それくらい気にしなくていいよ」といって、励ます
わが子を思っての行動ですが、どちらもNG。
急いで介入すると、かえって子どもの無力感が増したり、問題が深刻化したりする可能性があります。一方、問題を無視したり、軽視したりすると、子どもは相手の行為(=いじめ)を受け入れなければならないと考えるようになり、自尊心が損なわれる可能性があります。
私が息子に「あなたはどう思ったの?」と聞けたのは、偶然です。
内心「面倒なことになったな」と動揺し、時間稼ぎのつもりで聞いたのですが、功を奏しました。
子どもに話を聞くときのポイントは⬇️
- 何が起きたのか、本人が状況を理解しているか確認する
- それについてどう感じているのか、どうしたいのかを話してもらう
- 傷ついていたら、「悲しいよね、わかるよ」など共感の言葉をかける(=感情を言語化してあげる。
小学校低学年までの子どもは、共感という概念や、自分の言葉が他人に与える影響について理解し始めたばかり。つまり、あだ名をつけた子どもは、自分が害を与えていることに気づいていないかもしれません。
同様に、私の息子も、変なあだ名によって害を与えられたことを理解していませんでした。
複雑な状況だからこそ、ゆっくりと、まず話を聞くことが必要です。
状況が理解できたら、連絡帳やメールで園や学校の先生に連絡します。
電話で伝えると、「急いで解決しなきゃ」と要らぬプレッシャーを与えてしまいます。文書にするのは、証拠を残すためではなく、関係者に冷静に対処してもらうため。
ちなみに、私はこんなふうに記載しました。
いつも大変お世話になっております。
昨日、息子から「おともだちから、メガネマンというあだ名でよばれる」旨を聞きました。
詳しく聞いたところ、むしろ彼はあだ名を気に入って、かっこいいと思っているようでした。
しかし私は、外見および身体的特徴にもとづくあだ名は良くないと考えます。この価値観を先生方と共有したく、連絡いたしました。注意して様子をみていただけますと幸いです。
事実を報告し、自分の考えを伝え、先生に味方になってほしいことを伝えればOK。
変なあだ名をつけたお友だちを非難したり、先生方に怒りを向けたりすると最悪です。どんなにこちらに正当性があっても、「感じの悪い親だな」と思われ、味方になってもらえません。
あだ名問題の解決と、親にできる再発防止策
連絡帳を送ったその日の夕方、返事がありました。
教えてくださって、ありがとうございます。私たち職員も、そのようなあだ名は良くないという価値観をもっています。お迎えの際に、お話しさせてください。
味方ですよ、というメッセージです。安心しました。
お迎えに行くと、口頭でもお話しがありました。
「明日の朝の会で、外見に基づくあだ名についてどう思うか、みんなで話し合おうと思います」
息子の保育園ではレッジョエミリア・アプローチ(※)を採用しており、園生活で困っていることなど、よく子ども同士で話し合います。ですから、今回の件も議題に取り上げるということでした。
そして、私が考えを連絡帳でシェアしたことに重ねてお礼を言われました。
翌朝、さっそく園では話し合いが行われたようです。身体的特徴や外見をもとにしたあだ名の危害について、3〜5歳たちがより集まって考えを深めたそう。「メガネマン」という言葉は出さずに話し合いを進めていただいたおかげで、Sくんを責める構図にもならず、安心しました。
息子のクラスには外国籍の子もいます。早めに芽を潰すことができてよかったです。
子どもがあだ名問題で傷ついているとき、遊びがメンタルを癒してくれることがあります。カウンセラーに行くほどではないけど、どうしたらいいかわからない。そんな悩みには、こちらの記事をどうぞ。
「ちび」「のっぽ」「ブタ」「めがね」
名作と呼ばれるロングセラーの絵本にも、このような言葉が愛称として用いられているものは数多くあります。(ドラえもんとか、侮蔑表現の嵐ですよね・・・
個人的には、過去作品に遡ってまでポリティカルコレクトネスを推し進めるのには反対です。「昔はこうだった」と知ることにも、意味はあるからです。
ただ、なぜ昔は侮蔑表現が許容されていて、いまはダメなのかは説明しています。
市井の人の人権意識が高まったからなわけですが、これを3歳児にも伝えています。
世界中の民話をもとにした絵本や、優れた翻訳絵本がおすすめです。
福音館書店からは世界の民話や昔話をもとにした絵本が数多く発行されています。(モンゴルの『スーホの白い馬』、ロシアの『おおきなかぶ』など。)絵から多くのことが学べます。
(賛否両論ありますが)近年のアメリカの子ども向けコンテンツは、人種配慮が完璧に行き届いています。
トッド・パールの絵本『It’s Okay to Be Different』は、その代表格でしょう。
「禿げててもいいじゃん」「歯抜けでもいいじゃん」と、かんたんな英語でひたすら肯定します。わが家で1番最初に購入した洋書絵本です。
私の場合、問題をすぐに解決しようと焦らなかった結果、うまくいきました。
からかいに対応するだけでなく、尊厳や対人スキルの基礎をつくれたと思います。
適切な戦略があれば、親子ともに、困難を成長の機会に変えることができることを実感しました。もちろん、何もないのが1番ですが。声をあげたことで、次なる被害も防げて、大満足です。